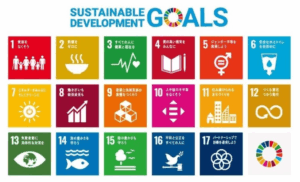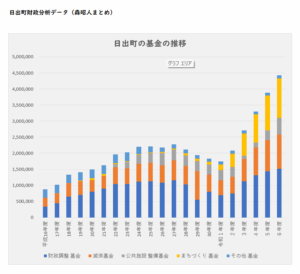SDGsの理念をもとに新たな漁業モデル

🌸今回、私が、3月定例会の一般質問で取り上げたSDGs未来都市への挑戦が実現し、選定されたことは大変喜ばしいことであり、持続可能なまちづくりに向けた大きな追い風であると考えています。
本町では、これまで、昨年10月の「日出町SDGs推進宣言」、12月の「ゼロカーボンシティ宣言」に見るように、主に理念の共有や啓発に取り組んできました。
しかしながら、今後は、未来都市に選定されたことで、「経済・社会・環境を統合する全国モデルの新たな事業」に取り組み、町民の皆さんにもその成果が実感できることが期待されます。
ひじの海から持続可能な未来

日出町は、国から「SDGs未来都市」に選ばれた町として、経済・社会・環境のバランスがとれた、持続可能なまちづくりを進めています。
その中でも、町の誇りであり、暮らしを支えてきた「海」と「漁業」は、まさに日出町の原点です。
近年、漁獲量の減少や魚価の低迷、後継者不足など、漁業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
それでも私たちは、先人たちが守ってきたこの海を、次の世代につなぐ責任があります。
町ではこれまで、アマモ場の再生活動や資源管理型漁業の推進など、「海のゆりかご」を守る取り組みを重ねてきました。
これらは、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」にも通じる大切な挑戦です。
これからの日出町の漁業は、単に魚を獲るだけではなく、「つくり・育て・守る」漁業へ。
そして、観光や教育、地域経済とつながる“新しい漁業モデル”へと進化していきます。
漁師さんたちが誇りを持って働き、子どもたちが海の仕事に憧れ、町外の人が「この海に来たい」と思う。そんな温かい循環を生み出すことが目標です。
私はその実現に向け、「浜プラン」のさらなる推進と、漁業の6次産業化を見据えた「海の駅 大神(仮称)」構想を提案しています。
魚を“売る”だけでなく、“つながる・学ぶ・楽しむ”場所として、海と人、地域と未来をつなぐ拠点に――。
「海の駅 大神(仮)」構想
朝市と観光・教育をつなぐ新たな拠点
日出町が誇る漁業の拠点・大神漁港では、地元の漁師さんたちによる朝市がほぼ毎日開かれ、多くの町民や観光客でにぎわっています。
朝どれの鮮魚を求めて足を運ぶこの場所は、まさに「海の恵みと人の出会いが交差する市場」であり、町の活力を支える大切な存在です。
しかし近年、来場者数は伸び悩んでおり、第2期「浜の活力再生プラン」で進めてきた朝市の活用――漁船クルーズ、体験ツアー、修学旅行の誘致など――も一定の成果を上げつつ、次のステージが求められています。
こうした中、今年6月には初めて、東京の私立高校の修学旅行生約50名を受け入れることができました。
漁船クルーズと朝市見学、そして新鮮な魚を使った朝ごはんを満喫していただき、参加者からも好評でした。
今回、「漁港の風景を眺めながら食事がしたい」という生徒さんの希望を受けて、屋外にテーブルとイスをセッティングしましたが、直射日光が差し込む場所での食事となり、今後の受け入れ環境について改めて考えるきっかけにもなりました。
雨天時には近隣の公民館を活用する予定ではありましたが、今後さらに受け入れの対象が広がり、小中学生の教育旅行や高齢者団体のツアーなどに対応していくためには、より快適で機能的な拠点づくりが不可欠です。
そこで私は、大神漁港の機能を大きくリニューアルし、「海の駅 大神(仮)」として再整備することを提案します。
単なる鮮魚の販売拠点ではなく、
- 雨天でも快適に過ごせる屋根付き多目的デッキと飲食スペース
- 修学旅行や観光客が体験できる調理・加工・食育施設
- 地元産品のPR・販売・発送に対応した観光交流・直売拠点
といった機能を整備することで、朝市の魅力をさらに引き出し、漁業の所得向上と地域経済の好循環を生み出すことができると考えています。
加えて、地元で水揚げされた魚をその場で加工・販売し、観光や食育とも結びつけることで、漁業のいわゆる6次産業化を本格的に推進することが可能になります。
その上で、漁師の方々や地元住民が主役となって、「獲って終わり」ではない、水産資源を最大限に活かす新しい地域モデルを築いていきたいと考えています。
観光や教育、ふるさと納税などとも連携した「未来の港まち」の新しい姿を描く、地域拠点再生プロジェクト。
今後も、漁協、水産業再生委員会・観光関係者をはじめ多くの皆さんと力を合わせ、地域資源を活かした漁業振興を進めてまいります。